Dum fata sinunt vivite
laeti.
運命が許す間、喜々として生きよ。
阿羅本 景
承前
Curatio vulneris gravior vulnere
saepe fuit.
-傷の治療は、しばしば傷そのものより大きな痛みをともなう-
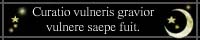
「う……ぁ……」
小さな呻き声を上げて、少年は羽毛布団の下で苦しげに身を捩った。
顔色が紅潮し、頬もかすかにこけている。目は堅く塞がれ、額に流れる汗の
粒も痛々しい。
ベッドの側に控える二人の少女は、心配そうにそんな病床の少年を見つめていた。
二人とも、顔立ちは驚くほど似通っている。一人は心配そうな顔で少年の額
を拭っては新しく冷やした手ぬぐいを当てるメイド服の少女。もう片方は和服
にエプロン姿だが、少年の腕を取り脈を真剣な顔で診ていた。
脈を取る手が熱い。和服の少女は知らず頭を振っていた。
メイド服の少女は、暗い室内でもその素振りを見逃さなかった。
「姉さん……」
「……翡翠ちゃん、命に別状はないはず……と言いたいのだけれども」
和服の少女の名前は琥珀、メイド服の少女は翡翠、という。
そしてこの病床にある少年の名前は、遠野志貴、といった――
§ §
館には魂がある。
棲んでいる者の息吹がそれであり、また歴史の重みがその魂であることも多
い。館から魂が抜けると、流水が巌を徐々に砕くように、沈滞がその空間を犯
していく。埃っぽい、人気のない廃屋の埋めがたい空虚な臭い。それは建築物
の死臭である。
遠野邸は、二人の双子の使用人を残したまま死臭に包まれていた。
戻ってきた遠野家の長男である志貴は、その系譜から消された幻の兄・四季
との戦いの末に姿を消した。それは、当主であり二人にとってはかけがえのな
い妹である遠野秋葉を生かすために――
そして、命を救われたはずの秋葉は、傷心を抱えたまま遠野邸を離れ、浅上
女学院に復学し寄宿舎に消えていった。まるで志貴の影を見続けることで傷つ
き続けることを恐れ、逃げるように。
そして、当主も消え去り、この屋敷には――魂が消え失せた。
二人の使用人がこの館を管理し、主無き館を常に清めていた。だがそれは器
を磨くだけであり、盛られる実は失せて久しい。
二人がいくら丹念に館の内を磨き上げようとも、忍び寄る腐朽の匂いは止め
ようがない。だが、二人は待ち続けた。この館に然るべき主が戻り、再び暮ら
せるその日の到来を信じているかのように……
琥珀も翡翠も、日々笑うことはなくなってきた。
沈滞した空気、誰もいない廊下。キッチンには主の食器の上に埃が積もる。
何時しか耐え難い雰囲気を発しはじめ、二人の神経が限界に達し始めてきたその時――
志貴が、帰ってきた。
だが、戻ってきた志貴は――十六歳の身体の青年ではなく、八歳の少年の身
体として。
その時、琥珀も翡翠も、変わり果てた志貴の姿に言葉はなかった。ほとんど
予告もなく唐突に戻ってきた志貴の方も、二人の使用人姉妹を前にばつの悪い
苦り切った顔をしているのみである。
一人、志貴を伴って戻ってきたシエルだけは面白そうな顔でこの三人を眺め
ているのでった。なにしろ、このシエルが失われた志貴の命を蘇らせるために、
八歳の身体に作り替えた張本人であるのだから……彼女だけはこういう事態を
予期していたと言っていい。
呆然とするばかりの二人に、要領を得ない志貴の説明と、簡潔だが超絶した
シエルの説明が交互し、翡翠も琥珀もようやく事のあらましが掴めたのであった。
あまりにも、予想を越えて変貌遂げて帰還した志貴ではあったが、二人にとっ
ては少年の志貴の姿には、まぶたが熱くなるのを禁じ得なかった。
少年の志貴――それは二人にとっての、幸せだったかも知れない時間の象徴。
琥珀も翡翠も志貴の青年の姿が失われたことを嘆くよりも、この志貴とこれ
からを過ごすことで、失われた八年の時間を取り戻せるかも知れない……そん
な風に感じたとしても、誰がこの二人の双子の姉妹を責められようか。
そして――
志貴が戻ってきたことによって、失われた筈の遠野邸の魂が戻ってきた。
琥珀も翡翠も、まだ己の身体に慣れない様子のある志貴に甲斐甲斐しく尽く
していた。特に翡翠は、曇りがちだった憂慮の顔を志貴に見せることはなく、
はにかむように笑うことが多くなっていた。琥珀も志貴や翡翠を見つめて、楽
しげな、時には胸の痛みを抑えるかのような顔を見せていた。
シエルは、二人の手に志貴を託すと名残惜しそうに去っていった。
『私から秋葉さんにはこのことを伝えておきます』と言い残したシエルであっ
たが、浅上女学院から秋葉はいまだ戻って来る様子はない。それが彼女なりの
意地の張り方だったのかもしれないが……
厳冬の季節は過ぎ、まだ淡い早春の息吹が遠野邸の庭に感じられる様になっ
たその頃。
志貴は――病み始めていた。
§ §
「志貴さま、お風邪を召されてますか?」
冬用の服を寝台の上に整えながら、翡翠は寝覚めの志貴に尋ねる。
布団から身体を出した志貴は、暖房が掛けられているにも関わらず冷たさの
ある空気に震え、軽く鼻をすすっていた。
すこしぼーっとした様子で志貴は翡翠を見上げていたが、すぐに頭を振る。
「いや、大したことはないよ。鼻風邪みたい
それに、あんまり心配することはないよ、翡翠……昔の俺とはちがって、ず
いぶん丈夫になったし」
少年の変声期を迎える前の声にも関わらず、変に大人びた口調は傍目にも可
笑しくはある。だが、翡翠は仕え初めて暫しは違和感を感じていた者の、すぐ
に慣れた。そして、幼い日の思い出のままの志貴に、いとおしさを隠せない目
で見つめている。
志貴は腕を出して力瘤を作ってみせるが、細い少年の身体の悲しさか、力強
さはまったく見られない。翡翠はその様子を見て笑いを浮かべるかどうか、一
瞬迷った表情を見せる。
だが、職業的な慣れゆえかすぐに仏頂面な、メイドの顔になる。
「お気をつけください、志貴さま。今の季節にお風邪を召されますと、長くこ
じらせかねませんので」
「はーい……じゃ、厚着してるよ」
「姉さんに頼んでお薬を貰って参りましょうか?」
「琥珀さんに?ああ、漢方の葛根湯かなにかかなぁ……宗玄のじーさんは『お
前ならこれくらいで十分じゃよ』とか言ってたけどね。じゃ、後で」
翡翠はベッドの上の服と下着を整え終わると、一礼して部屋から去ろうとする。
「それでは志貴さま。下でご朝を用意いたしておりますので」
「ああ、分かった……なぁ、翡翠」
ベッドに背を向けて歩き出そうとした翡翠は、呼び止められて振り向く。
「……何事でしょうか?志貴さま」
「いや……秋葉の奴、もうそろそろ戻ってこないのかなぁ、って……いや、翡
翠に聞いてもしかたないな、御免」
志貴は自分の喋った内容を恥じたかのように、ぷいと外を向いてしまう。
確かに、それは秋葉を覗いては神ならぬ身ではないと分からぬ事であろう……
だが、翡翠は敢えて口を開く。
「……秋葉さまは、悩まれておられるのではないのかと」
「……だろうな、俺はあいつにずいぶん酷いことをしたし……」
「いえ、志貴さまが思い悩まれることは何も。姉さんから聞きました、志貴さ
まはあの時ベストの選択をされたのだと……」
翡翠がきまじめな顔でそう志貴を励ます。
それは、つい志貴が弱気を翡翠に見せたときにいつも口にする言葉であった。
もともと饒舌ではない翡翠には、この程度の言葉が精一杯であった。
「……有り難う。翡翠。
その内、俺が秋葉を迎えに行く事も考えないとなぁ……ああ、頭痛いな」
「お風邪で頭痛がされるのですか?」
志貴が口走った言葉にすかさず反応する翡翠に、志貴は苦笑いした。
「いや、そうじゃないよ。じゃぁ、着替えたら下に行くよ
やれやれ、まだ学校にも行けないとヒマするな……」
「……それでは失礼いたします」
今度は深く頭を下げると、翡翠がドアから辞去する。
志貴はゆるゆると服を掴むと、寒い外に出るのが嫌そうに、布団の中で着替
えを始める。この辺は大人びた言葉とは裏腹に、子供そのままであった。
「さて、と……」
こざっぱりした格好でベッドから降りてきた志貴は、これも翡翠によって整
えられた靴に足を通す。そして、もう不必要になったが習慣となった眼鏡をサ
イドテーブルから拾い上げて掛ける。
その風景は――何も変わらない。死の線の見えぬ身体は有り難いが、昔日の
苦しみは名残惜しくもある。
そして、かすかに……死の線が見えぬということは、世界に騙されているよ
うな錯覚のような印象を志貴は覚える。死に満ち満ちた砂上の楼閣のような真
の世界は、死の影も見える偽りの平穏の足下でぐずぐずと崩れ去り始める……
そんな訳のない妄想。
――今もこの瞬間にも、死の見えざる手は俺の喉を掴んでいる
志貴は頭を振って余計な考えを追い払うと、絨毯を踏んで重い扉を押し、凍っ
たような冷たい空気の廊下を歩く。目線が低くなった分だけ、遠野邸の天井が
天のように高く感じていた。
「……石造だから冷えるんだよな、こんなに……」
吐く息が屋内でも白いのを見て、志貴は呟く。
早く歩いていかないと、階段を下りて食堂までたどり着く頃には骨まで冷え
切ってしまいそうだった。少年の身体にとっては、この遠野邸はやはり広い。
小走りになって階段を駆け下り、志貴は廊下を突き抜けて食堂のドアを開ける。
「あ、志貴さん、おはようございますー」
昼でも暗さの感じる廊下を抜けてきた志貴の目には、朝の光を湛える窓を背
負った琥珀の姿が輝いて見えた。暖房の入った食堂の空気の中に飛び込むと、
志貴はふっと身体の力を緩める。
「おはよう、琥珀さん。朝食の用意は出来ている?」
「はい、今お持ちします。イングリッシュブレックファーストで今日は決めて
みましたー」
「うん、それはいいねぇ……」
志貴が椅子に上がり、テーブルの上に用意された食器の前に着く。
やがて、奥の厨房から琥珀がトーストとスクランブルエッグ、サラダと紅茶
などを乗せたトレイを手にやってくる。
琥珀が軽く会釈をしてから整える間に、志貴はつと口に手を当て、くちゅん、
とくしゃみをする。
「あら、志貴さん……お風邪ですか?」
「ああ、翡翠からも聞いたかもしれないけども……ちょっと調子が悪いかも知
れない」
「それは大変ですねー、食後にお薬をおもちいたしますので、今日はゆっくり
されていては如何ですか?
それでは……どうぞ召し上がれ」
琥珀はてきぱきと食卓を整え、志貴に濃い朝のミルクティを差し出す。
こういう時の琥珀は、不思議と整理整頓が不得手な様子を見せていない。食
べ物が絡まないときの琥珀は、エントロピー増大の法則を地でいく活動をして
いるのだが……
「いただきます……へくちっ」
また小さくくしゃみをする志貴。
その様子を、後ろに控えた琥珀はクスクスと笑って見つめている。
「あらあら……お鼻が出てますよ?志貴さん」
「うー……恥ずかしいなぁ」
琥珀が袂から取り出したハンカチに軽く口元を拭われる様は、まるで……母
親とその子供か、あるいは年の離れた姉弟のようだった。
こんな、平穏な何気ない日常の光景。誰にも気がつかれないその時から――
志貴の病状は端を発し、そして彼の身体を蝕んでいった。
風邪で体調を崩した……最初は誰しもがそう感じていた、
だが、琥珀が風邪の処方をしても、志貴の病状は快癒の兆しを見せずに徐々
に悪化の途を辿っていった。発熱、頭痛、関節の痛み、食欲の減退、頭痛……
質の悪い風邪か感冒の類か、という琥珀の見立てを裏切り、志貴の体調は転
げ落ちるように悪くなっていく。だが、琥珀の目にも翡翠の目にも、志貴が何
を煩っているのかは判別の付けがたい所があった。
やがて、志貴はベッドから離れられない身体となってしまった。
一日に数時間目を覚まして僅かな食事をとる他は、苦しそうに喘ぎながら眠
るばかり。薬も僅かに症状を遅らせる程度にしか役に立たず、志貴は……見る
見るうちに衰弱ししていった。
まるで、根を切られた樹木が立ちながらも枯れていくように。
翡翠はもっぱら志貴の部屋に詰め、看病に努めていた。椅子に座り込んだま
ま眠り込み、琥珀に上掛けを掛けられると夜も何度もあった。
「大丈夫、心配ない。昔はこんな風になってもすぐに直ったから……」
目を覚ましたときに志貴は、こんな事を口にしていた。だが、翡翠はその言
葉を耳にすると、泣き崩れるのを堪えるのが精一杯であった。それほどに――
志貴の衰弱は進んでいた。
まるで、見えざる死の腕に絡め取られつつ有るかのように。
(To Be Continued....)
|