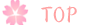キラ、キラ
作:大崎瑞香
卵焼きがとてもおいしそうにできたから、間桐桜はつい微笑んでしまった。
卵焼きを綺麗に焼くのはとても大変で、これなら先輩も褒めてくれるに違いない、と思うぐらいの出来映えだった。
ふと時計を見ると、もう6時30分。
もうこの時間とばかりに桜は慌ててエプロンを外すと、士郎の部屋へと走った。
襖の前に立つと、先輩、と声をかける。
しかし何の返事もない。そっと襖を開けて覗き込むと、士郎はいなかった。蒲団をひいた様子もない。
桜の眉がぴくりと少し動く。でも笑顔のまま。
(――まったくもう先輩ったら)
鍛錬の場である土蔵へと急ぐ。
(まだ病み上がりなのに――)
突っかけを履いて庭に降りると、まっすく土蔵へ。
死にかけたばかり、というより死んだ身の士郎はまだ体が慣れていない。なのに動けるからとついいつものとおりに振る舞ってしまうのだ。いくら魔法だからといったって、桜にしてみれば心配である。そうでなくても愛してやまない士郎は物事をとことんまでやってしまう性質なのだ。
桜からすればそんな士郎は心配で仕方がない。ライダーはあっさりと士郎も自分のことはわかっているはずですから、なんて言うけれども、やはり気になってしまう。
あんな大変な目に遭い、そして死に、そして蘇生したのだから。
ちょっと心配そうな顔をするとすぐに反省し、ぼそぼそと謝る。桜に迷惑をかけてゴメン、なんて、そんな顔をされて言われると、桜も何も云えなくなってしまう。そう思うのならしないでください、と言ってしまいたい。しかしそれはできなかった。
セイギノミカタというものを理想とし、それを目指し、そのために生きて。きた少年。真っ直で不器用で鈍感な愛しい人。そんな人が自分の理想を自分のために諦めてくれたのだと思うと、強く言うことなんて桜にはできなかった。
ちょっと不満はある。けれど、でもその不満もいつしか可愛らしく、愛しいものになってしまう。
(……まぁ先輩らしいといえば、いえるかな)
怒って少し吊り上がり気味だった桜の眉は少し下がった。
愚かなまでに頑固で一途な青年。それが桜の愛した彼なのだから。そんな不器用な性格もすべてひっくるめて好きになったのだから。
強い風が吹いた。
なのにそれはあくまで優しく、少し冷たいくせにどこか暖かい。そんな春の風。
そんな風を浴びて、桜は眼を細めながら空を見上げた。
真っ青な空。
春のものとは思えない鮮やかな蒼。蒼穹という言葉が相応しい、そんな天空に桜は微笑んだ。
もうすぐお花見だった。
待ちに待っていたお花見がすぐだった。
お花見なんて、という人もいるかもしれないけど、桜にとってそれは大切なものだった。先輩とのお出かけ。部活でも買い出しでもなく、出かけることが目的。
もちろんふたりっきりというわけではない。ライダーも藤村先生もみんな一緒。倫敦から帰ってくる姉の遠坂凛も一緒に行くことことになるだろう。
たぶん賑やかで、騒々しくて、けたたましくて、正直お花見どころではない。けれど、それはとても楽しい花見になるだろうというわくわくするような予感が桜にはあった。
桜は毎日が楽しかった。毎日が美しかった。毎日が素晴らしかった。
自分の取り巻く世界はあまり変わってはいない。自分は魔術師であり、聖杯と繋がっているために無尽蔵な魔力を秘めていて、英霊であるライダーを使い魔として契約していて、そして間桐(マキリ)の魔術の使い手。
聖杯戦争が始まる前と同じ。変わってはいない。
でも違った。
同じなのに、見方が変わるだけでこんなにも違うのかとびっくりするぐらい、まったく違ったのだ。
大聖杯と繋がっているからこそ、ライダーを維持できて、魔術師だからこそ先輩の肉体の変わりとなる人形を入手できた。
普通ならできないこと。普通ならあり得ないこと。それができた。
間桐の屋敷はすでに売り払ってしまった。そうしたら吃驚するぐらいのお金が口座に振り込まれた。こんなにお金があっても仕方がないのに、と思ったけれど藤村先生のお爺様は、なぁにあって困るもんじゃねぇ、もったいねぇから持っていな、なんて言ってくれて、ありがたくいただくことにした。
お金持ちになったところで、桜も士郎も何も変わりはしなかった。
こうしていつものように士郎のために食事を作って、士郎のこと思って怒って、そしてほがらかに笑い合う。
そんな輝ける日々。
そんなことを考えているうちに土蔵につき、そっと開ける。
薄暗い土蔵の中を覗き込んでみると、士郎がいつものようにそこで寝ていた。
もぅ、と桜は顔を膨らませる。
頑張るのは先輩の性分だから仕方がないけれどもこれじゃあ風邪を引いちゃいますよ、と叱ろうと思って、そっと近づく。
薄暗い土蔵の中。隙間から入り込む陽光による光と闇のコントラクトの中ですーすーと軽やかな寝息をたてながら寝ている士郎はあまりにもいつものとおりで。
ずっと前からみていた風景。
そしてこれからずっと見続けるであろう風景。
毒が抜けてしまった。
叱ろうと思っていたのに、こうして顔を見れるだけで桜は倖せになってしまう。
寝ている士郎の側に起こさないように静かに近づくと、そっと座り込む。
差し込む光の中、気持ちよさそうに寝ている士郎を、ずっとこのまま見ていたかった。
赤毛の愛しい人をそっと見つめる。
まるで聞き分けのないやんちゃ坊主を見つめるかのように眺め、彼の髪を撫でる。くすくったいのか唸る。けれどその顔に浮かんでいるのは笑顔。
歯を食いしばった辛そうな顔でもなく、慌てて必至になっている顔でもない、安らかな笑顔。
それを見ているだけで、倖せになってしまう。
こんなに倖せでいいのかしら? と桜が思ってしまうぐらい、こんなに普通で、こんなにも倖せ。
遠くから車の音が響いて、そして消えた。
残るのは彼と彼女の呼吸の音だけ。
暖かい光が射し込む中、桜はまた髪を撫でた。
むず痒いのか、それとも起きるのか、んん、と唸る士郎のそんな態度に、くすりと微笑む。
薄暗い土蔵の中、入り込む陽光によって浮かび上がる士郎はとても綺麗に思えた。
それは眩しくて、目映くて、キラキラと輝きに満ちていた。
なんてことない日常。
なんてことない、いつものこと。
こんな日がくるなんて桜は思ってもいなかった。
ううん、と桜は首をふって自分の考えを振り払う。
こんな日がくるのを夢見ていた。
けれどあり得ないことだと、ずっと諦めていた。
諦めることに慣れていたから。
遠坂家から間桐家へと養子として出された自分。
姉である凛と別れ、見知らぬ屋敷。そしてそこにあるマキリの蟲による魔術。
なんで、こうなの?
なんで、どうして?
わからなかった。わかりたくなかった。
わからないままに、何もかも諦めて、マキリの魔術を身に刻み込み、染みこまれた。
諦めれば楽になる。
諦めれば何も感じない。
自分には何もない。
親に捨てられた子。
親に引き渡された子。
何もないんだ、とそう思っていた。
けれど――。
あの真っ赤な夕暮れのグラウンドで、諦めることなく、納得するまで挑戦し続けた見知らぬ生徒。
あきらめればいいのに、なんて思った。
あきらめてしまえば楽なのに。
なのに生徒はどうしても納得いかないのか何度でもがむしゃらに挑んでいた。
幾度も、何度も、あきらめることなく。
ただひたすらに、ただがむしゃらに。
そんな生徒を見ているだけで、なんだか力が湧いてきた。違う、と桜は思った。力を分けて貰えたのだと思った。
目の前の寝ている愛しい青年をただ静かに見つめる。
でもこの人は諦めなかった。納得いくまで、諦めることなく、ただ挑む。
見ているだけでよかった。側にいるだけでよかった。
まるで本当の家族のように、藤村先生とこの人とわたしで一緒に過ごす日々。
それだけで力を分けて貰えた。
でもこれは夢。
家に言えれば魔術師としての鍛錬。蟲と交わり、兄に犯される日々。
こんな綺麗でキラキラとしたものなんて夢幻なんだ、と桜は思っていた。
だから、すべてが終わり、こうして恋人どうしになるだなんて――夢でしかなかった。
夢見るだけ。
ただそれだけだったはず。
なのに――。
こうして士郎とともにいられる日々が来た。
現実と夢が反転してしまったのではないか? と思ってしまうぐらい。
今でも夢を見ているのではないか、なんて思ってしまうぐらい。
そんな眩いぐらいキラキラとした世界に、桜はいた。
いつしか桜は微笑んでいた。
内側から滲み出て、溢れ出たしまったような、やさしい笑み。
この光輝く世界で、桜は愛しい人に微笑みかけていた。
ふと桜は思い立つと、そっと顔を士郎の耳に近づける。
言ってみたかった一言。
言い出せなかった一言。
『衛宮先輩』でも『先輩』でもない、なんてない一言。
どきどきする。
たった一言を、寝ているうちに囁くだけだというのに、こんなにも動悸が激しくなる。
「…………」
声にならなかった。けれども、桜の顔が真っ赤になる。暑くて、熱くて、汗が噴き出る。恥ずかしいのか、嬉しいのかそれさえも桜はわからない。
倖せなのに、さらにそれ以上をねだってしまう。
なんかとても罪悪感さえ覚えてしまうぐらい。
そっと士郎の様子をうかがう。
まだ寝ていた。気づいていない。もう一度だけ言える。今なら言える。今なら気づかれることなく、呼ぶことが出来る。
その薔薇色の唇がゆっくりと開き、たどたどしく、掠れた声で、桜は呼びかけた。
「…………し……し……し、ろう……さん……」
なんてない一言。
ただの呼び名。
なのに妙に気恥ずかしい。
先輩でもなく、恋人して名前を呼ぶという行為。
今後のことも考えれば、こんな風に呼べないといけないと思うのに、ついいつものとおりに先輩と呼んでしまう。
そう呼びたいわけでもなく、またそれが自然だからつい言えなかったけれども。
いつかはこう呼びたいと思っていた呼び方。
それがこうして寝ているとはいえ呼びかけることができて、照れてしまう。全身がむず痒い。恥ずかしくて、嬉しくて、思わずきゃーと言ってしまいそうになる。
「桜、どうし……」
「きゃーーーーーー」
桜は呼びかけられて思わず悲鳴を上げてしまった。
「なななななななななななな」
桜が振り向くと土蔵の入り口には陽光を背にライダーが立っていた。桜の悲鳴に吃驚して眼をまん丸くさせている。
「……ど、どうしたのですか、サクラ? 何かあったのですか?」
「い、いえ、何でもないのよ」
「――ん?」
士郎も悲鳴に目を覚ます。
「……何かあったのか?」
「いいんです、先輩!」
桜は顔を真っ赤にさせながら、きっぱりはっきり言い切る。
「でも桜。今の悲鳴……」
「そうです、サクラ」
「なんでもないんですってば」
あわあわと慌てながら、首をぶんぶんと音がなるんしゃないかと思うぐらい力いっぱい振って、否定する。
「せ、先輩。そ、そうです。今日は卵焼きがとてもおいしそうに焼けたんですよ」
じぃっと見つめる士郎とライダーの視線。それに真っ赤になりながらも微笑んで誤魔化す桜。
まぁ桜がそういうのなら、と士郎は起きあがる。
「サクラに士郎。失礼ですが、もう時間が……」
といってライダーは腕時計を見せる。すると午前7時をとっくに回っていた。
うわもうそんな時間? と士郎は慌てて土蔵の入り口へと急ごうとする。けど立ち止まると桜の方へ振り返った。
立ち上がろうとしていた桜はそんな士郎にきょとんとしてしまう。
いつもなら、すまない桜、と先に行ってしまうのに――。
がむしゃらで真っ直ぐな青年は先に行くこともなく、立ち止まると桜の方を見つめていた。
ついきょとんとしてしまう桜。
そんな桜に対して――。
えっ? という顔をしてしまう。
士郎がゆっくりと手を差しのばしてきたのだ。
ごつごつした男の人らしい大きな手を、しばしの間、桜は見つめると、はい、と頷いた。
恐る恐る手を握りしめる。
暖かく大きい手だと桜は思った。
小さくて可愛い手だと士郎は思った。
それだけで、なんだか二人して照れてしまう。
そんなふたりを見て、やれやれという表情のライダー。しかしその紫紺の瞳はとても優しい。その美しい口元に暖かい笑みが浮かんでいた。
遠くから車の音と同時に、士郎ったら朝ごはーんの時間だよー、早くしないと遅刻しゃうよー、という藤村大河の声が響いてくる。
そんな騒々しいくせに、どこか長閑ないつもの声に三人は笑い合い。
そして、三人は家へと向かった。
失ったものは多かった。でも得たものもあった。
たとえば今のような、桜の手をそっとでも強く握ってくれる愛しい士郎の手。
だから、桜はまた士郎に笑いかけた。
それを眩しそうに士郎を眺める。
あまりにも眩しくて、キラキラしていたから。
それは士郎が得たもの。
ふたりが得られたもの。
それはかけがいのないものばかり。
賑やかで、騒々しくて、けたたましい――。
そんな、キラキラ。
了
あとがき
かんたんな話ですみません。ぷちということで軽くいきたいと思い、また基本的に倖せいっぱい胸一杯でいきたいと思いまして。
いつものやわらかい話になりました。そのたにややインパクトや盛り上がりにかけるかも?
そんないつもの話ですが、楽しんで貰えたら幸いです。
また別のSSでお会いしましょうね。